【解答骨子】R4技術士(建設部門)勝手に出題予想(8)〜必須『インフラDX』〜
今回取り上げる出題予想テーマ
これまで過去問分析をしたり、予想したり、勉強資料・勉強法について綴ってきました。
今回は、実際に、出題予想テーマから想定問・解答骨子を作っていきたいと思います。
第ニ弾として出題可能性が特に高いと個人的に思っている、『インフラDX』について作ってみますね!
私もまだまだ未熟な技術者ですが、受験者の皆さまの頭の体操の参考にしていただけると幸いです。
(あくまでも私の勉強の仕方の一例という観点で見て下さい。A評価が取れるかは全くわかりませんのでご参考程度にしてください(苦笑))
インフラDX
今回は巷で話題沸騰の『インフラDX』について、取り上げたいと思います。
このテーマも『必須』『専門』どちらでも出題される可能性が非常に高いテーマだと考えています。
想定問作成
必須の方が汎用性が高いので、必須科目を想定して問い立てから始めていきたいと思います。
まずは、調べたりせず、自分自身でどれだけ解答を書けるか試してみましょうね。
問立て
近年、科学技術の進展は凄まじく、建設業界においても単なるIT化ではなく、デジタルトランスフォーメーション(DX)による建設生産プロセス全体の生産性の向上、業界の組織・風土の変革に迫られている。このような状況を踏まえて以下の問に答えよ。
(1)技術者として多面的な観点から3つ課題を抽出し課題の内容を示せ。
(2)最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する解決策を複数示せ。
(3)(2)で挙げた解決策をすべて実施したとしても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)(1)~(3)を業務として遂行するにあたり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。
解答骨子作成
ここでは『インフラDX』に関する問に対して、解答骨子を考えていきましょう!
なお、この解答骨子は、一旦調べずに書き上げ、用語などを後から調べて修正した程度のものです。
本番で書けるレベルを想定して作成していますので、自分自身でもまったく完璧ではないと思っていますが、よりリアルな解答骨子になっているのではないかと思います。その前提で一読いただけるとうれしいです。
まず、基本的な解答骨子の作り方は『施策背景』『課題』『解決策』で書いていくんでしたね。
この方針で解答骨子を作成していきます。
解答骨子
施策背景
デジタル化の推進にあたっては、現在、政府においてデジタル庁が設置されるとともに、「デジタル田園都市国家」が進められているところである。
また令和3年に新たに決定された『社会資本整備重点計画』においてもインフラ分野のデジタルトランスフォーメーションが横断的目標として掲げられたところである。
国土交通省所管分野においては、これまでも生産性向上を目指しi-Constructionの取組が進められてきているが、それに加えて令和2年に国土交通省に「インフラ分野のDX推進本部」が設置され、省内各局横断でデジタル・トランスフォーメーション(以下、「DX」という。)に関する取組の推進が図られているところである。
なお、同会議において、インフラ分野のDXは「社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現」と定義されている。
(1)3つの課題
『インフラDX』を進める上で重要な観点として、
- 建設生産プロセス全体の変革
- 発注者側のITリテラシーの向上
- リモートワークなどデジタル技術を駆使した新たな働き方の導入・定着
の3つを抽出する。
なぜなら、インフラDXの推進にあたっては、「建設生産プロセス全体・業務そのものを変革し、生産性の向上を図ること」「発注者側も新技術を現場に導入していくためのITリテラシー強化が求められていること」「リモートワークや遠隔臨場等、受発注者双方の働き方を変革し魅力ある建設業へと変えていくこと」が重要であるからである。
上記であげた観点に応じた課題としては、以下3つが考えられる。
- デジタル技術を活用した企画・計画・設計・施工・管理の各プロセス間のリードタイムの省時間化、各プロセスを効率的に実施するためのデジタル技術の導入
- 発注者側のBIM/CIMやプログラミング等のITリテラシーの不足
- 対面主義・書面主義を是正し、より効率的な働き方(リモートワークや遠隔臨場、遠隔施工等)を選択できるようにすること
【課題1】現状、企画・計画、設計、施工、管理とそれぞれの受託業者が前工程の成果物を参考に業務を遂行している。スムーズな引継ぎによる各生産プロセス間のリードタイムを少なくするため、BIM/CIM等3次元設計データを施工や管理へも活用できるようにすることが課題。また、各プロセスにおいても、建設業全体の最適化を図るため、協調領域の技術については各事業者間での共有化・共通化を図ることが課題。
【課題2】新技術を設計や施工業者が導入しようとした際、発注者に知識や経験が不足していることにより、導入の障壁となる場合が想定される。この障壁をなくすため、発注者側のITリテラシーを向上させるためのリカレント教育プログラム・研修等を組織的に取り組むことが課題。
【課題3】新型コロナウイルスの流行を受け、リモートワークやオンライン会議が業務で当たり前のように使われるようになったが、未だに国・自治体ともPCのスペック等環境が整っていないため、効率的な働き方を選択できない状況が散見される。今後、3次元データ等大容量のデータを扱う機会も増えてくることから、早急に労働環境を改善することが課題。
(2)最も重要な課題と解決策
最重要課題は、上記1であげた『建設生産プロセスの変革』と考えている。
なぜなら、『建設生産プロセスの変革』がインフラDXの最終目標であり、2024年の建設業界への残業時間規制の適用対応にも寄与する、既存の建設業界全体だけでなく建設業界以外の新たな参入プレーヤーへの波及効果が絶大であると考えられるためである。
解決策としては以下3点が考えられる。
- 設計段階へのBIM/CIMの導入による『フロントローディング』の実施、建設生産プロセス全体の工期・コストの縮減
- BIM/CIMを活用した『コンカレントエンジニアリング』を通じた建設生産プロセス全体の最適化
- 『協調領域の明確化・共有化』により各建設事業者のデジタル関連の開発・導入コストを抑える
【解決策1】BIM/CIMの原則化を通じた『フロントローディング』による設計等前工程の精度向上、施工の効率化による工期・コスト等の縮減
【解決策2】『コンカレントエンジニアリング』による全体最適を目指した発注方式(設計・施工一体型やECI方式)の導入推進
【解決策3】民間事業者による技術開発が進んでいるところであるが、『協調領域の明確化・共有化』により各建設事業者のデジタル関連の開発・導入コストを抑え、中小企業も含めた建設業界全体の効率化及び競争力の強化
(3)新たに生じうるリスクとそれへの対応策
上記(2)で述べた対策を実施しても残る新たなリスクとしては、『デジタルに関する新たな設備投資のできない中小建設関連業者の経営状況の悪化・魅力の減少による、地域の守り手としての担い手不足』と考えている。
現在、国土交通省を中心に基準類の整備が行われているところであり、例えばBIM/CIMは令和5年度に原則化されるなど、デジタル技術を活用することが当たり前の世の中になりつつある。
今はまさにその変革期にあたるが、財務状況に比較的余裕の無い中小零細企業における新たな設備投資が大きな障壁となっている。
この課題への対応策としては、
- 中小企業のデジタル技術導入にかかる費用に対する集中的な補助金投資による競争力強化
- 協調領域の基準類の整備・流通による新技術導入障壁の緩和
- 中小企業が受注する規模の工事の積算基準への新技術導入費用の計上による単体工事・業務における適正利益確保
などが考えられる。
(4)業務遂行にあたっての要件・留意点
『倫理、社会の持続性』の観点からは、以下の要件・留意点があげられる。
なお、技術士倫理綱領の『公衆の利益の優先』『持続可能性の確保』の観点も踏まえて述べることとする。
- 現在、政府の主要課題としてデジタル化と並んであげられていることとして、『国土強靱化』『カーボンニュートラル』が取り上げられている。
- 業務遂行にあたっては、国土強靱化の観点から、インフラDXの実現による『建設業全体の労働環境改善に伴う魅力向上(新3Kの実現)』、『災害復旧・復興を担う地域の担い手の確保』は非常に重要な点である。建設業従事者の減少・高齢化といった課題を解決する手段としてのインフラDXにも着目し、業務遂行にあたることが必要である。
- また、カーボンニュートラルの観点から、温室効果ガス排出量の少ない新たな建設機械を現場に導入し、脱炭素の取組に建設業も貢献していく必要がある。国土交通省では令和3年に国土交通グリーンチャレンジを定め、運輸業界・建設業界を巻き込んだ脱炭素・カーボンニュートラルの取組の展開がなされているところであり、この観点も踏まえ業務遂行にあたることが必要である。
(参考)技術士倫理綱領
【前文】
技術士は、科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。
技術士は、その使命を全うするため、技術士としての品位の向上に努め、技術の研鑚に励み、国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し、公正・誠実に行動する。
【基本綱領】
(公衆の利益の優先)
1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。
(持続可能性の確保)
2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。
(有能性の重視)
3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。
(真実性の確保)
4.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。
(公正かつ誠実な履行)
5.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
(秘密の保持)
6.技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。
(信用の保持)
7.技術士は、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。
(相互の協力)
8.技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。
(法規の遵守等)
9.技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。
(継続研鑚)
10.技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。
(参考)3義務・2責務
信用失墜行為の禁止、技術士等の秘密保持義務、技術士等の公益確保の責務、技術士の名称表示の場合の義務、技術士の資質向上の責務
解答のポイント
解答を作成する上では、1つの観点だけではなく、現在の主要な政策課題(官邸HPに載っているレベル)である、国土強靱化や脱炭素(カーボンニュートラル・GX)などの動きも踏まえたものとすることが、採点者側からしても採点しやすいのではないかなと考えています。
まとめ
今回は『インフラDX』についてとりあげました。
必須科目を想定しましたので、河川の視点というよりは全体像を意識した解答を作成しました。
政府の主要課題(防災・減災、デジタル、脱炭素)も組み合わせた解答を作成しましたので、勉強した内容を踏まえ、このようなあらゆる施策を組み合わせて解答できるように、自分の中で理解を深めておくと良いのではないかと思います。
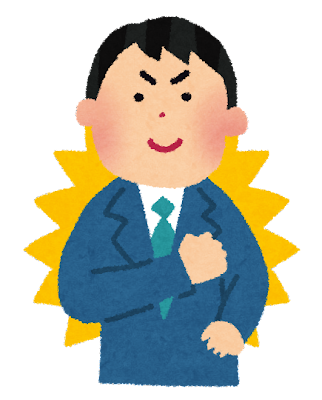
【R5年度 対策はこちらから↓】
R5年度技術士(建設部門_河川)(1)勉強法〜令和5年度水管理・国土保全局予算決定概要〜 | うつ×育児×転職×元官僚×技術士×ダム (ikujiojisan.biz)







